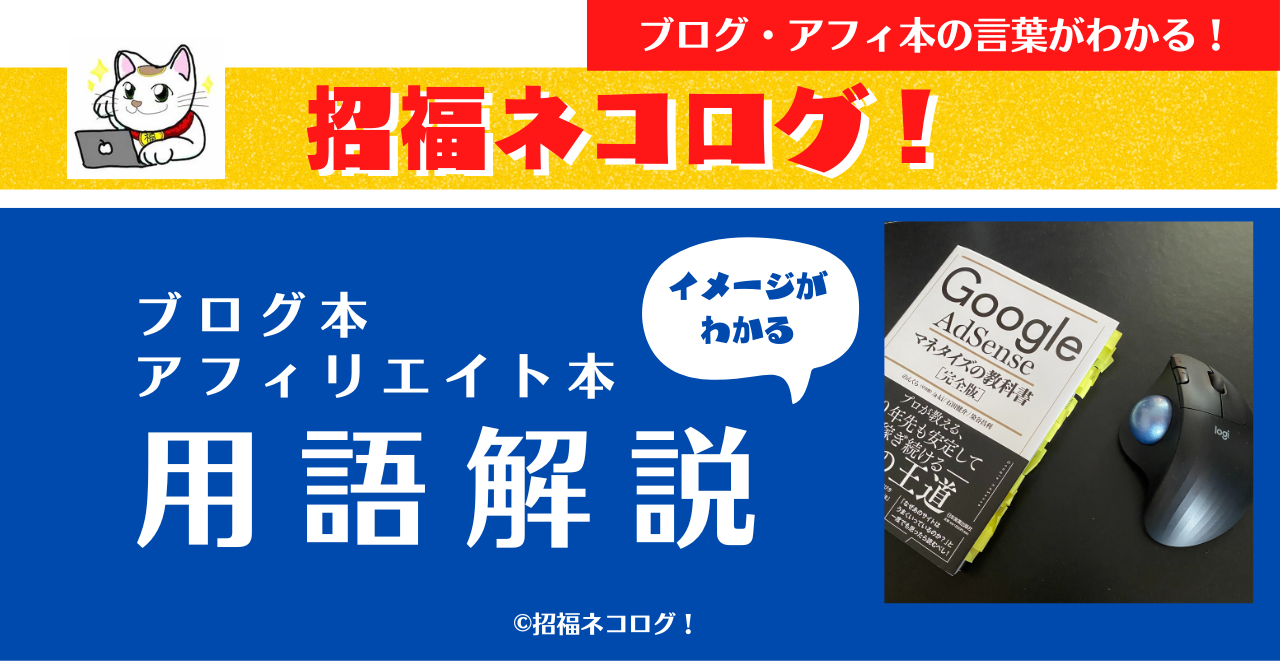ブログ本やアフィリエイト本を読むと、よくわからない言葉が出てきませんか。このページではそんなアフィリエイトブロガーのために専門用語をシンプルに解説します。

正確性よりも、イメージを優先して解説しています!地道に必要最小限の用語を追加していきます(つまり常に書きかけ)!
ブログ用語集(五十音編)
あ行
アーカイブ
過去記事のこと。ブログでは、新記事が優先的にトップページに表示されるため過去記事がトップから押し出されてしまうため、サイドバーなどにアーカイブ(過去記事)として月別などで表示させているブログが多い。逆に、日付順で表示させたくないブログ(サイト)を運営している場合は、アーカイブを非表示にすることができる。非表示するには、アーカイブのウィジットを削除するか、WordPress(ワードプレス)に設定しているテーマの投稿関連設定などで変更できる。
ちなみに僕(たくす)の場合、時系列の記事を書くことがあまりないため表示させていません。
アイキャッチ
記事ごとのタイトル画像のこと。記事一覧などでは縮小表示されるので、記事タイトルは大きめに書いておくと良い。アイキャッチ画像のサイズは一般的に横800px縦480px(px:ピクセル)や、横1280px縦670pxなど。あまり大きすぎると記事を開いたときに画像が画面いっぱいになるので注意。アイキャッチの作成は無料ツールのCanva(キャンバ)が人気で直感的に使いやすい。
アドセンス(GoogleAdSense)
グーグル社が運営している広告サービスで、成果報酬型(売れたら報酬が支払われる)のアフィリエイトとは異なり、広告が表示される回数で収益が発生します。2023年までは読者がクリックすると報酬が手に入るクリック報酬型広告でしたが、表示回数メインに変更となりました。
アフィリエイトよりも報酬額が低いものの、広告の張替えが不要であることが最大のメリット。広告内容もブログ訪問者の嗜好(しこう)や生活エリアに合わせたものに自動で切り替わることも大きなメリット。
放置ブログや完成させているサイトなどで多くのアクセスがあるなら、ぜひ使いたい収益源。
ただし、アドセンス広告を掲載するためにはブログやサイトをある程度作ってから、Googleに審査をしなければならない。近年は審査が厳しくなっていることが初心者を悩ませている。クリック報酬型広告はアドセンス以外にもあるが、アドセンスのほうが報酬が高いことがほとんど。

アカウント
ツイッターやインスタグラム、フェイスブックなどのSNS(ソーシャルネットワークサービス)の登録IDなどのこと。一部のSNSでは、複数のアカウントを持つことができるので、ブログ専用アカウントと趣味のアカウントを分けるといった使い方ができる。また、ブログ記事の宣伝のために活用するために、ブログテーマに沿った内容だけを発信するといった活用方法がある。アカウントのことをSNS上では「垢(あか)」と表現することがある。
アクセス数(訪問者数:PV数:ページビュー数)
ブログの訪問者数のこと。PV(ページビュー)と同様に、どれだけの訪問があったかを知る数字。アクセス数は「訪問者数」でPV数は「閲覧数」を示す。たとえば、1人の読者が3ページ見た場合は、1アクセス3PVというイメージ。もちろんどちらも多いほうが良い数字。
アナリティクス(GoogleAnalytics)
無料で使えるGoogle社のアクセス計測ツール。昔は有料だったが、現在は登録するだけで使える無料で高機能な計測ツール。計測できるのは「アクセスしてきた人」の情報。「検索してきた人」の情報は、グーグルサーチコンソール(Google Search Console:通称「サチコ」)で計測することができる。
どちらもGoogle社の無料サービスで、ブログの集客状況を把握するためには必須のツール。ただ、設定が細かい上に、Googleのヘルプが非常に分かりづらいため、基本的な設定と基本的な計測だけを使うことがベスト。2023年7月からアナリティクスは大幅アップデートしたため、従来のUAという計測ツールからGA4というバージョンへの設定移行が必要。最悪、UAを使用していた場合はGoogleがある程度まで自動設定することになっているので放置してみるのも一手。
アフィリエイト
ブログ記事などで商品を紹介し、記事に掲載している広告をクリックした読者が商品やサービス購入の申込みなどをすると、広告紹介料を報酬としてもらえるしくみのこと。アフィリエイト広告はASPと呼ばれる広告代理店のようなものに会員登録登録(基本的には登録や会費は不要)することで利用することができる。
アラート
注意表示のこと。エラー通知や危険を意味する黄色い三角形のマークなど。ワードプレスの更新通知やサーチコンソールのインデックス問題通知など。表示は画面上に表示されるものや、メールでの通知もある。必ずしもすべてを解決する必要はないが、自分なりに調べて解決しようと努力したいところ。
インデックス(フェッチ)
Googleなどの検索エンジンに、自分の記事を登録してもらうこと。内容の薄い記事や、他人の記事のコピー記事など価値がないと判断されると検索結果には表示されない。また、高品質な記事であっても公開するだけでは必ずしもインデックスされないことから、グーグルサーチコンソールを使って、新記事の登録を申請してインデックスを要請することができる。ただ、Googleなどの検索エンジンは、つねにインターネット上で高品質な記事がないかを自動で調査するプログラム(クローラー、巡回ロボット友いわれる)を使用しているため、申請せずともインデックスされることがある。
フェッチとは古い言い方で、インデックス登録申請とほぼ同じ意味。
インプレッション(インプ)
サイトで見られたページ数のこと。のべページ数で表現されるのが一般的。サイトが魅力的で、他のページへ移動しやすかったり、見つけやすい場合は、一人のアクセスで複数のインプレッションが発生します。SEO的には複数のページを見てもらうことが有利に働く(検索順位が上がる)と言われているため、見やすいデザイン、カテゴリ設定などを工夫することが吉。
ウィジット(追加機能)
WordPress(ワードプレス)などのブログツールでは、記事だけでなくカテゴリーやプロフィールなど、特定の内容をすべてのページで表示したい場合、標準画面に表示されない追加機能として、ブロガー自身が設置する機能のこと。
ウィジットの種類は多種多様で、カレンダー表示や新着記事一覧、特定の広告を表示させる、ブログ内検索窓を表示するなど便利なものが多数あり、ブログテーマによって特別なウィジットがある場合もあるので追加したくなるが、多用すると読者を迷わせることにもなるので必要最低限がベスト。
エクスポート(出力)
WordPress(ワードプレス)で言うエクスポート機能は、記事の情報をバックアップする場合などに、データとして一覧形式のデータを取り出せるもの。グーグルサーチコンソールなどのツール系の場合は、調査結果をダウンロードするときに使用する。Excel(エクセル)などの表計算ソフトで開けるCSV形式で取り出すことが多い。
オウンドメディア
企業が自社のホームページに掲載する情報発信コーナーなどのこと。古くは社長ブログなどから始まり、商品開発者のコラムや商品を活用した事例などさまざま。ブロガーからすれば強力なライバルと言える。
オーガニックサーチ(Organic:自然検索)
オーガニックとはブログの訪問者が検索して訪問してきた件数をいうもの。日本語では自然検索などと言われる。一般的には「オーガニック検索」と表現されることが多く、Googleなどの検索エンジンからの訪問を表示する。ちなみに「オーガニックソーシャル」ならSNS経由の訪問だと知ることができる。「ダイレクト」と表示されるのは、自分自身が記事を書くためにアクセスした数やブックマークされたアクセスを表す。
検索エンジン経由の訪問は、記事を公開してから半年後あたりから増えてくるので、ブログ公開直後はSNSで記事の宣伝をしたほうが良い。最終目標は、オーガニック検索数が90%を超えるサイトづくりでほぼ完全放置でも十分なアクセス数が見込める状態(記事内容が陳腐化しないことが前提です)。
か行
カスタマイズ
WordPress(ワードプレス)の標準機能を調整して自分の思い通りの表示をさせたりすること。カスタマイズはWordPress(ワードプレス)テーマの設定で行うこともできるが、細かな表示調整をしたり、簡単なプログラムを組み込んだりする場合はプログラミング知識が必要となる。代表的なプログラミング知識は、HTMLとCSS。さらにphp(ピーエイチピー)やjavascript(ジャバスクリプト)などが有名。ただし、身につけるには時間がかかるので、必須能力ではない。できる人に発注したり、ネットで検索して紹介されているプログラムなどをWordPress(ワードプレス)の該当する部分にコピー、ペーストするだけでもある程度の品質向上が可能。
キーワード(クエリ)
記事のテーマとなる単語や熟語などのこと。
読者がネット検索するときに検索窓に入力する言葉は「検索キーワード」と呼ばれ、クエリと表現されることもある。ライバルが少なく、検索する人が多いキーワードは「お宝キーワード」と呼ばれ、ブルーオーシャン(ライバルの釣り人がいない入れ食い状態の穴場)とともに語られることが多い。ブルーオーシャンの反意語はレッドオーシャンで、ライバルがキーワードを奪い合っている状況。キーワードの検索数を調べるには「検索キーワードツール」と呼ばれるサービスを使う。有料のものと無料のものがある。
クロール
Googleなどの検索エンジンが記事をインデックスするために検索ロボットがネットワーク上を巡回すること。記事をインデックス申請しなくても、高品質そうな記事がないかなと、あちこち巡回している。
ブロガーとしては早くインデックスされたいので、サチコでURL申請するほうが良い。
検索エンジン
インターネットの検索サービスを提供している各社の検索サイトのこと。
Google、Yahoo!、Bingなどが日本では利用されており、Yahoo!はGoogleの検索システムを利用しているため、実質はGoogleの一人勝ちが続いている。2000年頃はライブドア検索やニフティ検索など多種多様なものがあり、検索エンジンごとに上位表示のテクニックが異なっていた。
現在の日本ではGoogleの一人勝ち状態なので、検索上位表示させる工夫(SEO:検索エンジン最適化)はGoogle対策となっている。
さ行
サジェスト・サジェストワード
Googleなどで検索窓に検索したい文字を入力したとき、検索窓の下に表示される、予測される検索候補のこと。表示されるのは、2語以上の複合キーワードのように見えるため、みんなが検索している人気にーワードと勘違いしてしまいがちだが、実際は自分自身が検索している場所や、以前に検索したことのある結果などが表示されるため、人気のキーワードとは言えない。
キーワード選定を「検索数」でするのであれば、有料・無料を問わず、検索キーワードツールを使用する必要がある。
サチコ(GoogleSearchConsole)
グーグル社の無料アクセス解析ツールのことで、GoogleSearchConsole(グーグルサーチコンソール)を略した愛称。
どのような検索キーワードでアクセスされたかなど、ブログの集客状態が分析できる。Googleアナリティクスとともに、ある程度ブログ記事を公開したら毎日確認したい分析ツール。使用は、無料でGoogleアカウントを作成するだけで、自分のブログを登録すればいつでも確認可能。
サブディレクトリ
サブドメイン同様、メインドメインの良い影響を期待して新たな階層に別のサイトを作ること。SEO的に有利と言われている。
メインディレクトリとサブディレクトリの例は次の通り。
例)メインディレクトリ https://nekoneko.jp サブディレクトリ https://nekoneko/hogo.jp
WordPress(ワードプレス)のインストールは通常メインディレクトリだけにするが、サブディレクトリにもWordPress(ワードプレス)をインストールすることで、別のサイトを作ることができる。
サブドメイン
メインドメインの先頭に新たな文字を加わえて、別のドメインとして使うことからサブドメインと言われている。例えば、メインドメインのジャンルが株式投資で人気があるとき、サブドメインでFXなどの似たジャンルのサイトを作る場合に、メインドメインの良い影響があるとして、SEO的に有利と言われている。
メインドメインとサブドメインの例は以下の通り。
例)メインドメイン https://nekoneko.jp サブドメイン https://hogo.nekoneko/.jp
シークレットモード
検索履歴をパソコンに覚えさせたくないときに使うブラウザの機能のこと。通常は恥ずかしいサイトを見るお父さんのための機能。ブロガーとしての利用目的は、サジェストワードを残したくない場合や、WordPress(ワードプレス)で自分のサイトを何度も確認することでGoogleに「不正なアクセス」といった誤解を招かないために使う。
新しいブログを作ると、はじめの半年程度のアクセスは、ほぼ作業の確認のために自分が見たものだけになるため、「同じところからのアクセスがほとんど」と誤解されやすいために使う。一般的なアクセスが伸びてきたら気にする必要はない。
ステマ(ステルスマーケティング)
広告収入を目的として書かれている記事なのに、あたかも広告収入を得ずに純粋なレビューを書いているように見せる収入方法。本当は買ってもいないし、いいとは思っていないものでも「すごい!」「おいしい!」「コスパ最高!」などといい感想を書いて、実質は宣伝していること。
2023年10月に施行されたステマ規制法(景品表示法違反)として話題になった。アフィリエイターとしては、広告掲載しているページに「この記事は広告を含んでいます」といった文章を明記することで対応するのが一般的。
た行
タグ(タイトルタグ)
タグとは、ブログなどネット上で表示させるプログラム用語で、HTMLというプログラム言語の命令文の一つ…ってのは一般的な解説。ブロガーとしてはタイトルタグを知っておけば十分。
タイトルは「見出し」とも言われており、タグとの対比表を簡単に説明すると次の通り。
| タグ | 日本語 | よく使う役割 |
| H1 | タイトル | 記事のタイトル |
| H2 | 大見出し | 章タイトル |
| H3 | 中見出し | 段落タイトル |
| H4 | 小見出し | 段落内のタイトル |
タイトルタグはH1からH6まであるが、ブロガーとしてはH1からH4まで使い分ければ十分。
SEO対策としても有効と言われているので、タイトルには狙っているキーワードや共起語を含めて書くと検索順位が上がる可能性が高くなる。
WordPress(ワードプレス)でタイトルタグを使いたいときは、上部のリボンにある楽譜みたいなボタンをクリックして「見出し」を選択。すると、リボンに「H2」などを選択できるボタンがでてくるので、選択するだけです。ぜひ読みやすい記事を参考に、タイトルを工夫するのがおすすめ。
な行
ニッチ
ニッチ(すきま)とは、メジャーの反対語で、マーケティング上では「ニッチ産業」といった使われ方をする。ブログでは、テーマジャンルがメジャーでないものを意味する。
ブログのメジャージャンルはダイエット、クレジットカード、転職などの高単価報酬が狙えるようなものを指し、ライバルだらけ(レッドオーシャン)のジャンル。
一方、ニッチジャンルは、低単価でありながらもライバルが少なく、それなりのニーズがあるものを指す。いまや誰も選んでいないジャンルはほぼないものの、初心者でもすぐに検索上位が狙えるジャンルは多数ある。
ただし、見込み客の絶対数が少ないので、爆発的な成果には繋がらない。初心者なら練習を兼ねて「誰もこんなこと検索しないだろうなぁ」といったジャンルやテーマでひとつブログを書いてみるのはおすすめ。
は行
パーマリンク(WordPress用語)
投稿記事ごとのURLのこと。WordPress(ワードプレス)では自動で記事ごとにURLが作られるが、自動発行されるURLの形式(日付や記事ID、記事タイトルなど)は選択できる。WordPress(ワードプレス)をインストールしたら、はじめの記事を投稿する前にするべき初期設定の一つで、一度設定したら変更しない方が良い。なお、パーマリンクの自動発行形式はダッシュボードの一般設定から設定することができる。
ちなみに、記事タイトルで登録すると日本語が文字化けのように長文の意味不明なURLが発行されるので、できれば記事タイトルがわかるような英単語にするほうがいい。
発リンク(はつりんく)
自分のサイトから、他のサイトにリンクを貼ること。参照サイトはこちら、公式サイトはこちら、といったリンクのこと。自分のサイトから発信するリンクなので発リンクという。
SEO対策としては被リンクが注目されているが、発リンクも重要と言われている。
被リンク(ひりんく)
他のサイトやブログなどから、自分のサイトをリンクしてもらうこと。被リンクをもらう、リンクを貼ってもらうという。
被リンクを多く受けることで、そのジャンルで信頼できるサイトといった評価が高まると言われている。SEO対策に効果的と古くから知られている。
一方で、被リンクは昔、不正なSEOテクニックとしてネット界で流行していたため、リンクしてくれているサイトが無名であったり、全くジャンルが違うサイト、リンクそのものを販売しているサイトなどからの場合は、不正と判断され検索結果の表示対象から外される。
ブラックハットSEO
ズルい方法で検索結果の上位表示をねらうSEO手法のこと。昔は検索エンジン側の対策が行き届かなかったことから、多数のブラックハットSEOが流行した。
このため、検索しても知りたい情報がなかなか表示されず、商品販売ページやただのニュースのまとめ記事が上位表示される時代があった。このような「検索者が求めている結果を上位表示させたい」という検索エンジン側の努力で現在は多くのブラックハットSEOは通用しなくなっている。
ホワイトハットSEO
ブラックハットSEOに対して使われる言葉で、「有益なコンテンツ」ありきのSEO対策をいう。
自分がネット検索したときに、知りたい情報が正確で読みやすいものが上位表示されていると便利だと感じられることは、検索エンジン運営側が有益なコンテンツを探し続けているから。しかし、あなたの渾身の記事が検索エンジンから発見されない(場合によっては発見させない)ような設定になっていたり、検索エンジンが発見しても「テーマと文章がいまいち合ってないなー」と思われてしまっては元も子もないので、「有益なコンテンツかどうか正当に評価されるための工夫」と捉えておくとよい。
ブログアフィリエイターとして最低限知っておくべきことと、こだわりすぎなくても良いレベルがあるので、まずはタイトルと見出しのSEO効果だけでも知っておくと良い。
ま行
や行
有料テーマ
WordPress(ワードプレス)には、スマホの「きせかえ機能」のように、一瞬でデザインを変える事ができる「テーマ」をインストールして使うことが多いが、無料のものと有料のものがある。
無料のテーマで人気のあるCocoon(コクーン)、有料で人気のあるSWELL、JIN-Rなどは日本製で安心感がある。
なお、無料テーマは海外製のものも多数あるが、アップデート頻度が少ないものは、不具合が生じたりウィルス攻撃に弱い可能性があるのでおすすめしない。
また、テーマはデザインだけでなく、様々な機能があり、それぞれにメリット・デメリットが有る。あるテーマでできる表現が、別のテーマだとできないということが少なくないので、人気のあるテーマのどれか一つを使いこなすことがベスト。有料テーマは買い切りのものが多く、アップデートも基本的には無料でできる。
ちなみにこのサイトはCocoon(コクーン)を使用している。僕は複数のサイトを作っているので、別サイトではSWELLも使っている。

ら行
ランキングツール
自分のサイト内にある記事が狙っているキーワード検索結果で、Googleなどで何位に表示されているかを確認できるツール。ほぼ有料なので、初心者のうちは不要、アナリティクスでアクセス数を確認しておけばいい。記事数が増え、収益も発生してきたときは十分検討の上、活用するのがおすすめ。
有名なランキングツールは、GRC(ジー・アール・シー)だが、Mac版はないのでRankTracker(ランクトラッカー)を使う人も多い。ぼくはランクトラッカーを使っているが、年間1.5万円程度の利用費のわりに使いこなせていないのでやめようか迷っている。
わ行
ワードプレス(WordPress)
ブログを書くネット上の無料ツールで、記事として文章を書き、画像を貼り付けたものを手軽にネット上に公開することができる。自分が借りたレンタルサーバにインストールして使う。ほとんどのレンタルサーバで「かんたんセットアップ」という無料サービスがある。
WordPress(ワードプレス)は有料のものもあるので、自分でネットからダウンロードするよりも、レンタルサーバ内でセットアップを済ませてしまう方が確実。
なお、WordPress(ワードプレス)そのものは初期状態だと簡素なデザインなので、一般的には「テーマ」を選んで設定する。
また、テーマの有無に限らず、プログラミングを学べば、自分の好みにカスタマイズすることも可能で、参考図書も多数出版されている。簡単なカスタマイズであれば、ネット上に完成しているプログラム(コードと呼ばれる)が多数紹介されているので、コピペだけでカスタマイズすることも可能。
ブログツールはWordPress(ワードプレス)が世界的にもダントツだが、Movable Type(ムーバブルタイプ)、WIX、Jimdoなども有名。しかし、初心者はWordPress(ワードプレス)の1択。
ブログ用語集(アルファベット編)
A
Analytics
アナリティクスを参照。
AdSense
B
Bing
マイクロソフトウィンドウズ(Microsoft Windows)の標準ブラウザ「Edge(エッジ)」の、標準検索エンジン。
日本の検索エンジンはGoogle検索のひとり勝ちで、Yahoo!検索もGoogleの検索エンジンを使っている(2023現在)ため、マイクロソフトのEdgeはほとんど語られることがない。
しかし、Edgeからの検索数も少なからずあるので、インデックス登録しておくと良い。海外向けのサイトを作っているならぜひ登録しておきたい。
Buyクエリ
Buy(買う)クエリとは、すでに購入意思が高い人が検索するキーワードを指す。検索者はすでに商品やサービスに興味を持っているので、収益に繋がりやすい「今すぐ客」と呼ばれる。
ブログアフィリエイターとしては、Knowクエリでアクセスを稼ぎ、Buyクエリの記事に内部リンクを貼って導線を作るなどの工夫をするのが一般的。
C
D
E
F
G
H
J
I
K
Knowクエリ
Know(知る)クエリとは、キーワードの検索目的が「知りたい」止まりであるキーワードのことで、検索者は今すぐ購買しない。ブログアフィリエイターとしては、アクセス稼ぎのための記事にKnowクエリで記事を書く。収益につなげるためには購入ページへ誘導する必要がある。反対語はBuyクエリ。
L
LP(ランディングページ)
LP(ランディングページ)には2つの意味があります。
- 自分のサイトに検索で一番はじめにアクセスが有るページ。ランディング(着陸)の言葉通り、あなたのサイトに一番アクセスのあるページ(記事)のこと
- サイトの中で、商品を紹介するためだけに特化したページのこと。昔はLPの1ページだけを作成して、広告を使って申し込みさせる手法があり、たった1ページだけで収益化する手法として流行したことがあった。この場合はLPというより「ペラページ」という表現が多い
主に、サイトの中で商品紹介を促すページは1ページ作ることが多く、その他の記事はLPへ内部リンクを貼っておき、集客するためのページと申し込み促進のためのページを分けることが多い。これは、読者がどの記事を読んでも営業されている感覚が生まれないようにした工夫で、ブログ記事構成の基本的な考え方となっている。
M
N
O
P
Q
R
S
SEO(エス・イー・オー)
検索エンジン最適化と和訳される、検索結果上位表示のための様々な施策の総称。検索エンジンの上位に表示させることは、無料で狙った客層に自分のサイト訪問を促すコスパの良い集客方法なので、だれもが検索上位表示を望んでいる。2000年頃は誰でも検索上位表示させるテクニックが使えたが、現在は検索者に有益なサイトが表示されるようGoogle側も工夫をこらしているため、古いSEOテクニックは通用しない。
SEOという言葉は「裏技」「テクニック」の印象が深いため、詐欺がらみの話には注意。実際、SEOは検索者が読みたいと思う(だろう)正しい情報が、読みやすく書かれているサイトを上位表示するための検索エンジン側のノウハウであり、われわれブロガーやアフィリエイターが勝負する領域ではない。
価値あるコンテンツがGoogleで表示されないようにしないために、必要最低限の知識を持てば十分。
と、ぼくは思っている。